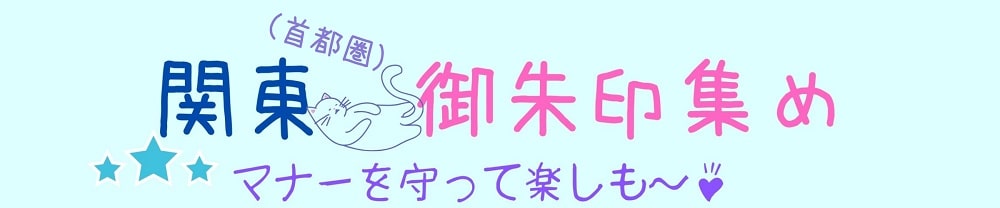御朱印集めをはじめました!
「御朱印集めが流行っているから御朱印集めを趣味にするの?」と聞かれると・・・それも一つの理由かもしれません。
ブーム(流行)になったから「御朱印」と言う言葉を知り、御朱印帳の存在を知りました。
しかし私的には、流行ではじめてよい事だとは思っていません。
そして今問題になっているのが、マナー違反をする人たちが多く、御朱印を中止する神社やお寺があるという事です。
そこで今回は、御朱印集めの本来の意味とマナーをまとめました。
御朱印集めをはじめると「ちょっとした疑問」が出てくると思うのでそれを解決しておきたいと思います。
(お賽銭の金額についての豆知識もあります)
真剣に御朱印集めをはじめようと考えている人の参考になると思います。
御朱印集め!御朱印について
御朱印を集めると「何となく良い事がありそう!」などという考えだけでは、それこそブーム(流行)だからはじめる人と同じになってしまします。
ここでしっかり、御朱印の事を理解しておきましょう。
御朱印とは?
墨で書いた文字と、印が捺されています。
本来なら、写経をご本尊様に奉納した証としていただけるのが御朱印です。
(写経とは、仏教経典を書き写した物です)
今は、お参りをした証としていただけるようになりました。
(今のブームのせいではなく、かなり昔から習慣になっていたそうです)
御朱印をいただく本当の意味
今は何と!観光スポットに行った記念として、スタンプを集める感覚で、御朱印をいただく人が増えているそうです。
これって違いますよね?
今は写経を奉納する事をしないとしても、自分自身が参拝(お参り)をし、ご縁を結んだ証としていただくのが、御朱印をいただく本来の意味ではないでしょうか?
その為にも、しっかりマナーを守り、
御朱印をいただかないといけませんよね。
御朱印をいただく時のマナーの確認
御朱印は御祭神や御本尊の分身とされ神聖なものになります。
御朱印をいただくにあたり、マナーを守れない人も多くいるそうで、御朱印を中止する神社やお寺が増えてきているのが現状です。
御朱印集めをはじめるのなら、マナー(ルール)をしっかり確認しておきましょう。
(とはいえ、当たり前の事も含めてご紹介します)
参拝を先に行う
大変失礼な人がいるようで、参拝もせずに御朱印を先にいただく人や、御朱印だけいただく人がいるそうです。(これにはビックリですよね)
ただし、神社によって御朱印帳を先に預けてから参拝する!というところもあるので、事前に確認しておきましょう。
補足:参拝の前に手と口を清める事を忘れない様に!
御朱印をいただく時
御朱印をいただける場所で「御朱印をいただけますか?」など伝えて、書いてほしいページを開いてお渡しする。(ページを開く事を忘れがちなので気を付けましょう)
御朱印をいただく場所
神社の場合:社務所
お寺の場合:寺務所(納経所)
などになりますが、今は「御朱印受付」など案内がある事が多いです。
御朱印代を支払う時
金額が解らない時は「おいくら納めればよろしいですか?」と尋ねましょう。
一般的に300円~500円です。おつりが必要ない様に小銭を必ず用意していきましょう。
あっ!現在は神社やお寺の諸事情につき「お札を出しておつりをもらう」パターンもあります。
お金を払ったから御朱印をもらえるのが当たり前!この考え方はやめましょう。
御朱印はお金で買う物ではない!
「参拝(お参り)をして結んだご縁に対して納めさせていただき、その証として御朱印をいただく」という考え方にする方がよいと思います。(個人的な意見です)
御朱印を書いていただいている時
お友達(グループ)で御朱印集めをされる人たちに多いそうです。
御朱印をお願いした時は「静かに待つ」守りましょうね。
これはマナー違反にもなりますし、他の人の迷惑になるので注意しましょう。
そして「飲食をしないで待つ」というのが、御朱印を集めている人たちの中では常識?とされているようです。
御朱印帳を受け取る時
御朱印を受け取る時には「ありがとうございます」など、お礼を伝えましょう。
この時、書いていただいた御朱印を確認すると思いますが、ネットなどで見た御朱印と違うなど、文句や愚痴をいう人がいるそうです。
これはかなり失礼な言動でマナー違反です。
筆耕者が何人もいる神社やお寺はたくさんあり、それにより書体や書法も変わるという事は知っておきましょう。
御朱印集めの注意点
御朱印というのは全ての神社やお寺でいただけるものではありません。必ず訪れる前に確認しましょう。
- 御朱印をいただけるのか?
- 御朱印をいただく時に納める金額
- 御朱印をいただける時間帯
- 御朱印をいただく場所
などを確認しておくとよいと思いますよ。
イベント(行事)などがある時期は御朱印を中止している事や・・・
・半紙にすでに書かれてある御朱印(書き置き)
・イベント(行事)や季節などの特別御朱印
など普段と違う事があるので、注意しましょう。
御朱印集め!疑問を解決
御朱印集めをはじめようと思ったけど、確認したい事っていくつかありますよね?
そこで、疑問に思う事や知りたいと思うような事をまとめました。
御朱印帳を忘れてしまったら?
御朱印をいただく為に予定をたてる人が多いと思いますが、予定にはなかったけれど参拝(お参り)する時もあると思います。
参拝(お参り)した証として御朱印をいただきたいですよね?そんな時は、
「半紙に御朱印をいただけますか?」と聞いてください。
絶対いただける!とは言えませんが、ほとんど御朱印をいただけます。
御朱印帳は両面使えるの?
両面使用する事はマナー違反にはなりませんが、使用している御朱印帳の種類により裏に滲む可能性があります。個人的な意見ですが、御朱印帳は両面使わない方がよいと思います。
神社とお寺(寺院)御朱印帳を分けるべき?
御朱印を分けないとマナー違反になる!という事はありません。
しかし知っておかないといけない事があります。
日本では「神仏習合」の考え方の方が多いが「神仏分離」という考え方もあるので、神社とお寺(寺院)一緒の御朱印帳では書いていただけない場合があります。
無理にお願いする事はマナー違反になります。
個人的な意見ですが、御朱印集めを本格的に行うのなら、2冊用意する方がよいと思います。
御朱印を複数いただくのはマナー違反?
複数いただく事はマナー違反ではありませんが、混雑している時期(時間帯)の場合には、複数の御朱印をいただけるか?確認してからお願いしましょう。
1日にいくつもの神社やお寺の御朱印をいただくのはマナー違反?
マナー違反ではありません。
しかし御朱印をいただくだけを目的とするのではなく、参拝する事を目的としなくてはいけません。
自身の気持ちにより、マナー違反となる可能性はありますよ。
同じ神社やお寺の御朱印を何回もいただいてよいの?
参拝した証としていただくのが御朱印なので、以前書いていただいたとしても、もう一度御朱印をいただく事は何も問題がありません。
イベント(行事)や季節ごとに違ったデザインの御朱印を書いていただけるので、それを楽しみにされている人も多くいます。
御朱印帳の保管の仕方に決まりがある?
神棚や仏壇に置く(保管)のが正しいといわれています。
御朱印は御祭神や御本尊の分身ですからね!
しかし、神棚や仏壇がない家が多いのではないでしょうか?
そのような時は、御朱印帳を保管する場所を決めておけばよいと思います。
バッグに入れっぱなし、出しっぱなしという事がない様にしましょう。
お賽銭の金額について
御朱印集めに必要なお賽銭の金額が気になりませんか?
一般的には、5円(ご縁があります様に・・・)と5円玉を1枚奉納する事が多いと思いますが、豆知識としてお賽銭の語呂合わせを記録しておきます。
- 5円玉2枚:重ね重ねご縁があります様に!
- 5円玉3枚:15円なので、十分にご縁があります様に!
- 5円玉4枚:よいご縁があります様に!
- 5円玉5枚:25円なので、二重にご縁があります様に!
枚数が増える事で語呂合わせがたくさんありますが、ここまでにしておきます。
注意したいお賽銭の金額
10円玉(とおえん)という事で、縁が遠のく(遠ざかる)と言われています。
5円玉がなく、10円玉があるからといって1枚奉納しない方がよいですね。
10円玉を使用するのなら、1円玉と一緒に奉納しましょう。
- 11円:いいご縁!
- 21円:夫婦や恋人と一緒に奉納すると縁が切れない!
- 22円:二重にご縁!
などの語呂合わせもあるようです。
実は500円玉も要注意!
これ以上大きな硬貨がない事から「効果がない」とされています。
最後に
御朱印集めが話題になってから、常識的な事もできないマナー違反をする人たちが増えているそうです。
御朱印集めは、神社やお寺に「参拝(お参り)し、ご縁を結んだ証としていただく」この気持ちを忘れずに、マナーを守って楽しみたいですよね。